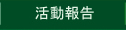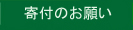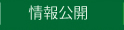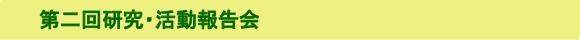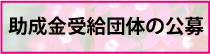(財)緑の地球防衛基金 第2回研究・活動報告会を開催

大石会長あいさつ
(財)緑の地球防衛基金は、「いま名もない砂漠がふえている、私たちは次の世代へ緑の地球を贈ろう」をスローガンに、設立目的である森林の破壊と砂漠化を防ぐことを中心に1991年から㈱オーエムシーカードと協力して、関係団体に助成を行ってきています。そこで、日頃の研究・活動の成果として、去る4月12日(土)13時から東京・田町のTKP田町ビジネスセンターにおいて「緑の地球をまもるために」の第2回研究・活動報告会(テーマ「明日のために何ができるか」)を開催しました。今回は、第1部の基調講演では(独)森林総合研究所の松本光朗温暖化対応推進室長から「地球温暖化を防ぐ森林の役割」について、また第2部の活動報告では、田野倉達弘ヒマラヤ保全協会事務局長から「ヒマラヤの自然を守る活動」、南研子熱帯森林保護団体代表から「ブラジル・アマゾン地域の植林事業」、馬場繁幸国際マングローブ生態系協会理事長から「島嶼国におけるマングローブ生態系の保全・再生に関する調査と植林活動」について発表がありました。そして、最後に、涌井史郎桐蔭横浜大学特認教授(当基金常任理事)から総括がありました。多くの質疑があり、盛会に終わりました。
なお、(独)森林総合研究所の松本光朗温暖化対応推進室長からの「地球温暖化を防ぐ森林の役割」の要旨は次のとおりです。
地球温暖化を防ぐ森林の役割
(独)森林総合研究所 温暖化対応推進室長 松本光朗

IPCC第4次評価報告書は、現在の地球温暖化が温室効果ガスの人為的増加によるものであるとほぼ断定した。その主因は石油・石炭などの化石燃料の使用であり、その削減が第一の緩和策となる。一方、排出削減とは反対の方法として、森林によるCO2吸収という緩和策がある。植物は光合成により大気中のCO2を吸収して育つ。樹木は数十年から数百年にわたってCO2を吸収し、炭素を体内に蓄え続ける。蓄えられた炭素は、その後、伐採や枯死、腐朽、燃焼を通して再び大気に還って行くが、同じ土地で次の世代の森林がまた吸収、蓄積を繰り返す。つまり、個々の林木は短期に吸収と排出を繰り返しながら、森林全体としては長期間にわたり安定的に炭素を蓄え、大気中へのCO2排出を調整していると言える。
地球全体の炭素循環を見てみると、森林を主とする陸域生態系の植生と土壌には2兆2600億トンの炭素が蓄えられている。大気中の炭素が7600億トンであることから、いかに多くの炭素が陸域に蓄えられているかが分かる。また、化石燃料の使用による排出64億トン/年に対し、吸収は陸域と海洋による32億トン/年であり、地球全体の収支では32億トン/年の排出となっている。陸域に注目してみると、毎年の収支は生態系による26億トンの吸収と土地利用変化による16億トンの排出により、正味10億トン/年の吸収となっている。ここで、土地利用変化とは、森林を伐採し農地や市街地などに転用する森林減少を意味している。森林減少による炭素排出量は総排出量の20%を占め、化石燃料の使用に次いで大きいことから、森林減少の削減が最近注目されいる。このような地球上の炭素循環の全体像を見れば、地球温暖化における森林の重要性が理解できよう。
森林・木材の貢献
森林は、光合成により大気中のCO2を吸収するという基本的な機能を持つが、森林はその状態や取り扱いによって吸収源にも排出源にも成り得る。若い林は成長が旺盛で吸収量も大きいが、原生林や極相林といった成熟した森林では、成長による吸収量と枯死による排出量がほぼ同量となる。森林の伐採は木材の利用を経て最終的に燃焼や腐朽により排出につながり、森林火災や病虫害は短期間に大きな排出をもたらす。ただし、いずれもその後に森林が再生すれば、排出された分は再び吸収され、中長期的には差引ゼロになる。ここで、森林分野での一番の問題は森林減少である。森林減少は森林の伐採による排出をもたらすだけでなく、将来の吸収や蓄積の機会も奪うためである。
さて、CO2を吸収して生産された木材は、その一方で排出削減をもたらす。木材は住宅や家具といった形で炭素を蓄積する。また、鉄やアルミのように製造時に大きなエネルギーを必要とする材料に代えて、製造エネルギーが小さい木材を利用することにより、化石燃料の使用量を節約することができる。例えば、鉄筋コンクリートの代わりに木造で住宅を立てれば、半分以下のエネルギーですむ。さらに、化石燃料の代わりに木材を利用してエネルギーを作れば、その分の化石燃料の使用量を減らすことができる。このことから、木質残廃材を使ったバイオマスエネルギーに注目が集まっている。
このように、地球温暖化に対する森林分野の貢献は、森林・林業・木材利用という一連の流れのなかで、森林による吸収と木材利用による排出削減という、両面からのアプローチによるものであることが大きな特徴といえる。このような認識を背景に、IPCC第4次評価報告書では森林・木材の緩和策として、①森林面積の維持・増加、②林分レベルでの森林蓄積の維持・増加、③ランドスケープレベルでの森林蓄積の維持・増加、④木材製品の活用、を掲げている。
日本での緩和策
さて、日本ではどのような緩和策が適用できるだろうか。まず、森林面積の維持・増加であるが、日本の森林面積はこの数十年間その変化はほとんど無く、面積維持はできるにしても増加は難しい。伐採後の確実な更新や耕作放棄農地への植林が、わずかな対策となろう。
森林蓄積の維持・増加はどうだろうか。戦後に造林されたスギ、ヒノキ、カラマツといった人工林は、高い成長量、すなわち高い吸収能力を持ち、現在、大きな吸収源となっており、この人工林による吸収状態を長期的に維持することが現実的である。このとき、人工林の間伐が十分には実行されていない現状が懸念される。適切に間伐されなければ林木は細くモヤシのようになり、台風や病虫害によって被害を受けやすく、つまり排出の危険性が高くなる。人工林の多い日本では特に、間伐は健全性と吸収源を維持するための重要な緩和策と言える。
一方、木材製品の活用による排出削減の潜在力は、木材の増加により200万炭素トン/年、建築物の木造率を現状の35%から70%に上げることにより200万トン/年、現状の木質系残廃材をエネルギー利用することにより200万炭素トン/年、計600万炭素トン/年と推定されている。これは森林の炭素吸収量の25%にもあたる。しかし、現状では木質系エネルギーの利用はコスト面での課題が多く、実現には技術開発とともに税制や補助金などの政策の導入が不可欠であろう。
京都議定書と森林
2007年5月の報告によれば、2005 年の森林によるCO2吸収量は8750万トンであり、総排出量に対して6.4%にあたる。しかし、京都議定書報告においては、この吸収量をそのまま排出削減目標の達成に使えるわけではない。1990年以降に実施された新規植林・再植林活動や森林経営活動といった条件に合致した森林の吸収量を、1300万炭素トンを上限として用いることができることになっている。これらの条件を考慮して算定したところ、2005年において、京都議定書による吸収量の総計はCO2換算で3545万トン(炭素換算967万トン)の吸収であった。つまり、森林経営活動による吸収量の利用の上限に対し、現状ではその74%にとどまっていることになる。この結果をふまえ、上限値まで吸収量を獲得するため、林野庁は追加的な間伐推進策を進めているところである。
途上国における森林減少
近年、炭素排出量の20%をもたらす森林減少が注目されている。IPCC第4次評価報告書は、森林分野における緩和策は潜在量の約65% が熱帯にあり、約50%が森林減少の削減と劣化の防止により達成可能としている。しかし、京都議定書は、熱帯を含む途上国の森林減少を止める仕組みを持っていない。そのため、2012年以降の次期枠組みに向け、この問題をREDD(途上国における森林減少による排出の削減)と呼び、国際的な議論が行われてきた。
昨年、インドネシアで開かれたCOP13において、REDDに関する合意がなされた。その主な内容は、途上国の森林減少と森林劣化を対象として、途上国が森林減少を回避・削減できれば、その量に応じてインセンティブ(報奨)をクレジットや資金などの形で得られるという仕組みを作るというものである。途上国からはREDDの仕組みは歓迎されているが、排出削減量の推定に係わる技術的問題や、インセンティブの与え方、各国のガバナンスの問題など実行上の問題がまだ山積みの状態であり、先行きを楽観視できない。